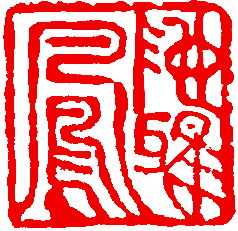この文章では、アプサラスと呼ばれる天界の存在についての伝説、神話、歴史を探ります。彼女たちは文化、宗教、地域を超えて登場し、沈黙のジェスチャーと優雅な動きによって表現される美の象徴として共通の意味を持っています。
古代インドの叙事詩『ヴァールミーキ・ラーマーヤナ』のバールカーンダ章では、宇宙的な神話「サムドラ・マンタン(乳海攪拌)」が語られています。神々とアスラ(悪魔)は本来敵対する存在ですが、不死の霊薬「アムリタ」を得るために一時的に協力します。彼らは天の蛇ヴァースキをマンダラ山に巻きつけ、綱のように引っ張り合いました。山は回転し、原初の海をかき混ぜ、まるでクリームからバターを作るような動きでした。
この宇宙的な混沌から、多くの驚異が生まれました。神々、宝石、そして天界の存在たち。その中には繁栄の女神ラクシュミーもおり、彼女はヴィシュヌを永遠の伴侶として選びました。これは保存と豊かさの融合を象徴しています。ヴィシュヌはヒンドゥー教の至高神の一柱であり、宇宙とダルマ(宇宙秩序)を守る存在です。彼は創造神ブラフマー、破壊神シヴァとともに三神一体「トリムールティ」を構成します。
医薬の神ダンヴァンタリも乳海から現れ、アムリタを入れた器を携えていました。彼は神々の医師とされ、ヴィシュヌの化身の一つでもあります。また、インドラが戦いの前に好んで飲んだとされる霊薬「ソーマ」も登場します。これは神聖な植物から作られ、力、霊感、不死性をもたらすとされました。
この原初の混沌から生まれた驚異の中でも、アプサラスは特に際立っています。彼女たちは美そのものの娘とされる、儚く輝く存在です。
別の神話によれば、アプサラスはブラフマーの目から120人創造され、舞によって宇宙の調和を回復するために送り出されました。ブラフマーは彼女たちを天界の宮殿ヴァイジャヤンタへ導き、嵐と魔術の神であり天界の王でもあるインドラに託しました。
アプサラスはインドラとその妃インドラーニを楽しませるために舞を披露しました。彼女たちの芸術は、ヴィグナ(邪悪な霊)を遠ざける力があるとされました。文献によっては、舞台芸術の各分野を象徴する26人のアプサラスがいたとも記されています。
最古のヴェーダ文献である『リグ・ヴェーダ』では、アプサラスは「天の貴婦人(スヴァルヴェーシャヤー)」と呼ばれています。彼女たちは天界スヴァルガに住み、空気の精霊であり神の音楽家でもあるガンダルヴァと共に暮らしていました。彼らはしばしばアプサラスの伴侶とされます。また、音楽の才能を持つ半人半鳥の神話的存在キンナラ、放浪詩人チャラナ、魔法の賢者ヴィディヤーダラ、戦死した英雄、徳ある王たちも共に登場します。
スヴァルガは、徳、音楽、芸術が神聖な恩寵と共存する広大な神々の世界として描かれています。それは宇宙の中心であるメル山の上に存在すると信じられており、神話上の七つの大陸「ドヴィーパ」の中心でもあります。
『シヴァ・プラーナ』によれば、アプサラスはヒマラヤの天界都市に豊富に住む神々であり、シッダ(瞑想と苦行によって超自然的な力「シッディ」を得た霊的存在)と共に、リュートや太鼓に合わせて喜びに満ちて舞っているとされています。
『ヴィシュヌ・プラーナ』や『マツヤ・プラーナ』などの物語では、アプサラスは聖仙カシャパ・ムニとその妻の間に生まれたとされ、天界の妖精たちの系譜を形成します。地上に生まれたものの、父によって天界へ導かれ、スヴァルガに迎え入れられました。別の文献では、彼女たちはメル山に住むとされます。伝統によっては、愛の神カーマデーヴァが彼女たちの支配者とされています。近年の物語では、アプサラスはヴィシュヌの化身クリシュナの舞の伴侶「ゴーピー」とも結びつけられ、その優雅さと献身が称えられています。
『ブラーフマナ』文献では、アプサラスは聖なる木々の間に住むとされ、植物界と結びついた精霊として自然に根ざしています。
この宇宙的な混沌から、多くの驚異が生まれました。神々、宝石、そして天界の存在たち。その中には繁栄の女神ラクシュミーもおり、彼女はヴィシュヌを永遠の伴侶として選びました。これは保存と豊かさの融合を象徴しています。ヴィシュヌはヒンドゥー教の至高神の一柱であり、宇宙とダルマ(宇宙秩序)を守る存在です。彼は創造神ブラフマー、破壊神シヴァとともに三神一体「トリムールティ」を構成します。
医薬の神ダンヴァンタリも乳海から現れ、アムリタを入れた器を携えていました。彼は神々の医師とされ、ヴィシュヌの化身の一つでもあります。また、インドラが戦いの前に好んで飲んだとされる霊薬「ソーマ」も登場します。これは神聖な植物から作られ、力、霊感、不死性をもたらすとされました。
この原初の混沌から生まれた驚異の中でも、アプサラスは特に際立っています。彼女たちは美そのものの娘とされる、儚く輝く存在です。
別の神話によれば、アプサラスはブラフマーの目から120人創造され、舞によって宇宙の調和を回復するために送り出されました。ブラフマーは彼女たちを天界の宮殿ヴァイジャヤンタへ導き、嵐と魔術の神であり天界の王でもあるインドラに託しました。
アプサラスはインドラとその妃インドラーニを楽しませるために舞を披露しました。彼女たちの芸術は、ヴィグナ(邪悪な霊)を遠ざける力があるとされました。文献によっては、舞台芸術の各分野を象徴する26人のアプサラスがいたとも記されています。
最古のヴェーダ文献である『リグ・ヴェーダ』では、アプサラスは「天の貴婦人(スヴァルヴェーシャヤー)」と呼ばれています。彼女たちは天界スヴァルガに住み、空気の精霊であり神の音楽家でもあるガンダルヴァと共に暮らしていました。彼らはしばしばアプサラスの伴侶とされます。また、音楽の才能を持つ半人半鳥の神話的存在キンナラ、放浪詩人チャラナ、魔法の賢者ヴィディヤーダラ、戦死した英雄、徳ある王たちも共に登場します。
スヴァルガは、徳、音楽、芸術が神聖な恩寵と共存する広大な神々の世界として描かれています。それは宇宙の中心であるメル山の上に存在すると信じられており、神話上の七つの大陸「ドヴィーパ」の中心でもあります。
『シヴァ・プラーナ』によれば、アプサラスはヒマラヤの天界都市に豊富に住む神々であり、シッダ(瞑想と苦行によって超自然的な力「シッディ」を得た霊的存在)と共に、リュートや太鼓に合わせて喜びに満ちて舞っているとされています。
『ヴィシュヌ・プラーナ』や『マツヤ・プラーナ』などの物語では、アプサラスは聖仙カシャパ・ムニとその妻の間に生まれたとされ、天界の妖精たちの系譜を形成します。地上に生まれたものの、父によって天界へ導かれ、スヴァルガに迎え入れられました。別の文献では、彼女たちはメル山に住むとされます。伝統によっては、愛の神カーマデーヴァが彼女たちの支配者とされています。近年の物語では、アプサラスはヴィシュヌの化身クリシュナの舞の伴侶「ゴーピー」とも結びつけられ、その優雅さと献身が称えられています。
『ブラーフマナ』文献では、アプサラスは聖なる木々の間に住むとされ、植物界と結びついた精霊として自然に根ざしています。
12th-century sandstone apsara statue, Madhya Pradesh, India.
Image: MET DP-1062-001 — CC0 license.
水から生まれた一歩・アプサラとその名
霧から生まれ、空に舞うエーテリアな存在
アプサラスの名前の由来には、いくつかの説があります。 叙事詩『ラーマーヤナ』によれば、これらの天女は「乳海」と呼ばれる神聖な海の本質 rasa から生まれたとされます。その海が宇宙的にかき混ぜられる現象は apsu と呼ばれます。 この apsu と rasa の融合から apsurasa が生まれ、それが「アプサラス(Apsara)」という名前の語源となったのです。意味は「水から現れる者」— 原初の混沌から生まれた優雅さの化身です。 一方、『リグ・ヴェーダ』では、アプサラスは太陽に引き寄せられた蒸気や天の霧として描かれ、それが凝縮して透き通るような舞う姿になったとされています。
アプサラスには主に2つの種類があります:
ダイヴィカ(Daivika):神聖な存在で、乳海攪拌から生まれたもの
ラウキカ(Laukika):地上に生まれ、自然界に宿る存在。カシャパ仙人の子孫とされる者たちも含まれます
後者の中には ヴリクシャカ(Vṛkṣaka) と呼ばれる森の精霊もおり、旅人を魅了し、時には破滅や死へと導く神秘的な案内人とされています。
どの神話においても、アプサラスは儚く美しい存在として描かれています。 彼女たちは優雅さ、美しさ、そして変容の象徴であり、若々しく、洗練され、舞踊芸術に長けた超自然的な女性像です。
彼女たちの舞は単なる芸術ではなく、神聖な儀式です。 それは喜び、誘惑、宇宙の調和を象徴するものであり、娯楽のためではなく、世界のバランスを保つために舞われます。 人間の時間や論理には従わず、変化のために、そして結びつきのために舞うのです。
また、彼女たちは地球の美しさと祖先の記憶の守護者でもあります。 宇宙の永遠のリズムを通してそれらを讃え、豊穣の儀式にも関わっていたとされます。 物質と霊、身体と霧の境界に住む存在とも言われています。
アプサラスは プラバーヴァ(prabhāva) と呼ばれる超自然的な力を持ち、美しさだけでなく、運命を変え、芸術的創造を促し、苦行を中断させる力もあります。 舞、音楽、詩に秀でており、人間、動物、植物など、あらゆる姿に変身できるとされ、特に白鳥の姿で現れることが多いです。
その起源、性質、役割によって、アプサラスは神聖な文献や神話の中心的存在となり、強いカリスマ性と神聖な使命を持って描かれています。
叙事詩『マハーバーラタ』では、複数のアプサラスが重要な役割を果たします。 例えば ティロッタマ(Tilottama) は、互いに殺し合うことでしか死ねない強力な悪魔の兄弟を滅ぼすために創造されました。 彼女が現れると、兄弟は彼女に恋をし、最終的に互いを滅ぼします。 この物語は、欲望が宇宙の秩序を回復するほどの力を持つことを示しています。
『ラーマーヤナ』では、アプサラスの メナカー(Menakā) が、神インドラによって仙人ヴィシュヴァーミトラの瞑想を妨げるために送られます。 彼女は彼の前で舞い、歌い、彼を魅了して瞑想を破り、共に暮らすようになります。 その結びつきから生まれたのが、インド文学で愛される存在 シャクンタラー(Śakuntalā) です。 この物語では、メナカーは単なる誘惑者ではなく、愛と変容の物語の中で「恋する女性」として描かれます。
その他の文献、例えば古代のヴェーダやプラーナ文献では、さらに多くの物語が語られています。 最も有名なのは ウルヴァシー(Urvasi) の話です。彼女は王 プルーラヴァス(Purūravas) に恋をし、「彼女の前で裸になってはならない」という条件で共に暮らすことに同意します。 ある日、その条件が偶然破られ、ウルヴァシーは空へと消えてしまいます。 彼女は年に一度だけ戻り、子を授けますが、約束が破られたために永遠には留まりません。
別の物語では、ウルヴァシーが戦士 アルジュナ(Arjuna) を誘惑しようとします。彼は神インドラと王妃クンティの子であり、パンダヴァ五兄弟の三男です。 アルジュナは彼女を優しく拒絶し、ウルヴァシーは怒って彼を呪います。
アプサラスには主に2つの種類があります:
ダイヴィカ(Daivika):神聖な存在で、乳海攪拌から生まれたもの
ラウキカ(Laukika):地上に生まれ、自然界に宿る存在。カシャパ仙人の子孫とされる者たちも含まれます
後者の中には ヴリクシャカ(Vṛkṣaka) と呼ばれる森の精霊もおり、旅人を魅了し、時には破滅や死へと導く神秘的な案内人とされています。
どの神話においても、アプサラスは儚く美しい存在として描かれています。 彼女たちは優雅さ、美しさ、そして変容の象徴であり、若々しく、洗練され、舞踊芸術に長けた超自然的な女性像です。
彼女たちの舞は単なる芸術ではなく、神聖な儀式です。 それは喜び、誘惑、宇宙の調和を象徴するものであり、娯楽のためではなく、世界のバランスを保つために舞われます。 人間の時間や論理には従わず、変化のために、そして結びつきのために舞うのです。
また、彼女たちは地球の美しさと祖先の記憶の守護者でもあります。 宇宙の永遠のリズムを通してそれらを讃え、豊穣の儀式にも関わっていたとされます。 物質と霊、身体と霧の境界に住む存在とも言われています。
アプサラスは プラバーヴァ(prabhāva) と呼ばれる超自然的な力を持ち、美しさだけでなく、運命を変え、芸術的創造を促し、苦行を中断させる力もあります。 舞、音楽、詩に秀でており、人間、動物、植物など、あらゆる姿に変身できるとされ、特に白鳥の姿で現れることが多いです。
その起源、性質、役割によって、アプサラスは神聖な文献や神話の中心的存在となり、強いカリスマ性と神聖な使命を持って描かれています。
叙事詩『マハーバーラタ』では、複数のアプサラスが重要な役割を果たします。 例えば ティロッタマ(Tilottama) は、互いに殺し合うことでしか死ねない強力な悪魔の兄弟を滅ぼすために創造されました。 彼女が現れると、兄弟は彼女に恋をし、最終的に互いを滅ぼします。 この物語は、欲望が宇宙の秩序を回復するほどの力を持つことを示しています。
『ラーマーヤナ』では、アプサラスの メナカー(Menakā) が、神インドラによって仙人ヴィシュヴァーミトラの瞑想を妨げるために送られます。 彼女は彼の前で舞い、歌い、彼を魅了して瞑想を破り、共に暮らすようになります。 その結びつきから生まれたのが、インド文学で愛される存在 シャクンタラー(Śakuntalā) です。 この物語では、メナカーは単なる誘惑者ではなく、愛と変容の物語の中で「恋する女性」として描かれます。
その他の文献、例えば古代のヴェーダやプラーナ文献では、さらに多くの物語が語られています。 最も有名なのは ウルヴァシー(Urvasi) の話です。彼女は王 プルーラヴァス(Purūravas) に恋をし、「彼女の前で裸になってはならない」という条件で共に暮らすことに同意します。 ある日、その条件が偶然破られ、ウルヴァシーは空へと消えてしまいます。 彼女は年に一度だけ戻り、子を授けますが、約束が破られたために永遠には留まりません。
別の物語では、ウルヴァシーが戦士 アルジュナ(Arjuna) を誘惑しようとします。彼は神インドラと王妃クンティの子であり、パンダヴァ五兄弟の三男です。 アルジュナは彼女を優しく拒絶し、ウルヴァシーは怒って彼を呪います。
分かち合う一歩、アプサラ、霊、そしてアジアの根
アプサラスは仏教の伝統にも登場します。特に東南アジアでは、霊的存在に満ちた地域の宗教実践の中で現れました。これらの存在は人間と神々の間に位置し、仏教儀式と神秘的・芸術的な生活との豊かな融合に貢献しています。
これらの半神的存在は デーヴァター(Devatā) と呼ばれ、木々や川の曲がり角、石の中に住むと信じられています。彼らは宇宙のさまざまな層—死後の世界、地上、空気、天界—に住み、自由に行き来するとされます。人間と結婚したり、世界間の使者となったり、人体や聖なる場所、隠された宝物の守護者としても描かれます。ただし、彼らが善良であり続けるためには、敬意と感謝の儀式が必要であり、怒りを避けるためには和解の儀式も求められます。
多くの地域社会にとって、今日でも世界はこうした霊的存在で満ちています。彼らは生きていて、活動的で、人間の生活に深く関わっています。仏教の地域的な実践は、こうした霊の崇拝を受け入れ、その存在に適応することで、仏教がアジア全域に広がる助けとなりました。
仏陀の前世を語る『ジャータカ物語』では、アプサラスやその類似の天界の存在が登場しますが、彼らは控えめで二次的な役割を果たします。人間とは異なる次元に存在するとされながらも、彼らもまた 輪廻(サンサーラ) のサイクルに従っています。
特に東アジアやインドシナでは、アプサラスは融合的な過程を通じて仏教の図像に取り入れられました。彼女たちの姿は、中国、カンボジア、タイ、インドネシアの仏教寺院で見ることができます。
仏教の極楽浄土では、天人(Ten'nin) と呼ばれる天界の存在が、仏陀や菩薩の伴侶として登場します。その中には神話的なデーヴァターも含まれています。天人(Tennin) という言葉は仏教経典にも登場し、日本の美術、彫刻、演劇における彼らの描写の基礎となっています。
日本では、これらの存在が中国の図像から取り入れられ、天女(Ten'nyo) と呼ばれています。彼女たちは日本の絵画や彫刻に頻繁に描かれ、演劇作品にも影響を与えています。
能の演目『羽衣』では、天女が地上に降りて羽衣(hagoromo)を脱ぎます。物語では、漁師が彼女を見つけて羽衣を隠し、天界に戻れなくなった彼女は彼と結婚します。数年後、漁師が真実を告白し、天女は羽衣を取り戻して空へ帰っていきます。
日本の描写では、天女は並外れた美しさを持つ女性として描かれ、優雅な着物、洗練された装飾品、長いスカーフを身にまとっています。彼女たちはしばしば 蓮の花(精神的な悟りの象徴)を持ち、琵琶や笛などの楽器を奏でます。
カンボジアの文化では、アプサラスは人々の集団的な想像力に深く根付き、広く知られる存在となりました。カンボジアの伝統では、彼女たちは テップ・アプサー(Tep Apsar) と呼ばれ、「テップ」は神聖を意味します。
ここでも、彼女たちの存在は伝説から始まります。カンボジア人が、仙人 カンブ(Kambu) と、シヴァによって遣わされた天女 メラ(Mera) の結びつきから生まれたという創世神話です。この神話は、舞踊、神性、そして国家のアイデンティティを結びつけています。
バクセイ・チャムクロン寺院 は、クメール王朝をメラに結びつけ、神聖な血統を強調しています。アプサラスは、カンボジア帝国 カンブジャ(現在のアンコール)の神話において特に重要な存在でした。
クメールの伝説によれば、王 ジャヤヴァルマン2世(カンブジャ王国の創設者とされる)は、インドラから王国を授かりました。その瞬間、アプサラスはカンブジャの人々に舞踊の技術を教えたとされます。それ以降、これらの天界の半神たちの姿は、アンコールの多くの寺院の壁に石で刻まれるようになりました。
彼女たちの浮き彫りは、デーヴァターと同様に多くの寺院で見られます。特に アンコール・ワット では、約1850体ものユニークなアプサラスの彫刻が存在し、それぞれが異なる姿をしています。アプサラスが乳海から誕生したという伝説も、アンコール・ワットの壁画に描かれています。
アプサラスは神話から生まれ、無常の中で舞い、神々と人間を喜ばせます。彼女たちはアンコールの石壁から私たちを見つめ、インドネシア、中国、日本、東南アジアの各地で出会うことができるかもしれません。
しかし、彼女たちは皆、共通の神話的本質を持っています: 心を揺さぶるほど美しく、心を溶かすほど優雅で、ジェスチャーだけで語る存在 — それが彼女たちの芸術です。
これらの半神的存在は デーヴァター(Devatā) と呼ばれ、木々や川の曲がり角、石の中に住むと信じられています。彼らは宇宙のさまざまな層—死後の世界、地上、空気、天界—に住み、自由に行き来するとされます。人間と結婚したり、世界間の使者となったり、人体や聖なる場所、隠された宝物の守護者としても描かれます。ただし、彼らが善良であり続けるためには、敬意と感謝の儀式が必要であり、怒りを避けるためには和解の儀式も求められます。
多くの地域社会にとって、今日でも世界はこうした霊的存在で満ちています。彼らは生きていて、活動的で、人間の生活に深く関わっています。仏教の地域的な実践は、こうした霊の崇拝を受け入れ、その存在に適応することで、仏教がアジア全域に広がる助けとなりました。
仏陀の前世を語る『ジャータカ物語』では、アプサラスやその類似の天界の存在が登場しますが、彼らは控えめで二次的な役割を果たします。人間とは異なる次元に存在するとされながらも、彼らもまた 輪廻(サンサーラ) のサイクルに従っています。
特に東アジアやインドシナでは、アプサラスは融合的な過程を通じて仏教の図像に取り入れられました。彼女たちの姿は、中国、カンボジア、タイ、インドネシアの仏教寺院で見ることができます。
仏教の極楽浄土では、天人(Ten'nin) と呼ばれる天界の存在が、仏陀や菩薩の伴侶として登場します。その中には神話的なデーヴァターも含まれています。天人(Tennin) という言葉は仏教経典にも登場し、日本の美術、彫刻、演劇における彼らの描写の基礎となっています。
日本では、これらの存在が中国の図像から取り入れられ、天女(Ten'nyo) と呼ばれています。彼女たちは日本の絵画や彫刻に頻繁に描かれ、演劇作品にも影響を与えています。
能の演目『羽衣』では、天女が地上に降りて羽衣(hagoromo)を脱ぎます。物語では、漁師が彼女を見つけて羽衣を隠し、天界に戻れなくなった彼女は彼と結婚します。数年後、漁師が真実を告白し、天女は羽衣を取り戻して空へ帰っていきます。
日本の描写では、天女は並外れた美しさを持つ女性として描かれ、優雅な着物、洗練された装飾品、長いスカーフを身にまとっています。彼女たちはしばしば 蓮の花(精神的な悟りの象徴)を持ち、琵琶や笛などの楽器を奏でます。
カンボジアの文化では、アプサラスは人々の集団的な想像力に深く根付き、広く知られる存在となりました。カンボジアの伝統では、彼女たちは テップ・アプサー(Tep Apsar) と呼ばれ、「テップ」は神聖を意味します。
ここでも、彼女たちの存在は伝説から始まります。カンボジア人が、仙人 カンブ(Kambu) と、シヴァによって遣わされた天女 メラ(Mera) の結びつきから生まれたという創世神話です。この神話は、舞踊、神性、そして国家のアイデンティティを結びつけています。
バクセイ・チャムクロン寺院 は、クメール王朝をメラに結びつけ、神聖な血統を強調しています。アプサラスは、カンボジア帝国 カンブジャ(現在のアンコール)の神話において特に重要な存在でした。
クメールの伝説によれば、王 ジャヤヴァルマン2世(カンブジャ王国の創設者とされる)は、インドラから王国を授かりました。その瞬間、アプサラスはカンブジャの人々に舞踊の技術を教えたとされます。それ以降、これらの天界の半神たちの姿は、アンコールの多くの寺院の壁に石で刻まれるようになりました。
彼女たちの浮き彫りは、デーヴァターと同様に多くの寺院で見られます。特に アンコール・ワット では、約1850体ものユニークなアプサラスの彫刻が存在し、それぞれが異なる姿をしています。アプサラスが乳海から誕生したという伝説も、アンコール・ワットの壁画に描かれています。
アプサラスは神話から生まれ、無常の中で舞い、神々と人間を喜ばせます。彼女たちはアンコールの石壁から私たちを見つめ、インドネシア、中国、日本、東南アジアの各地で出会うことができるかもしれません。
しかし、彼女たちは皆、共通の神話的本質を持っています: 心を揺さぶるほど美しく、心を溶かすほど優雅で、ジェスチャーだけで語る存在 — それが彼女たちの芸術です。
時に寄り添い、再び生まれるデーヴァター
アプサラスの物語は、物語が終わるところで終わりません。 彼女たちは、彼女たちを見つめる人の目の中で、探し求める人のジェスチャーの中で、そして言葉よりも雄弁な沈黙の中で、今もなお舞い続けています。 そして、もしかすると、世界のどこかで、彼女たちは今も舞っているのかもしれません。
アプサラのギャラリーに戻る